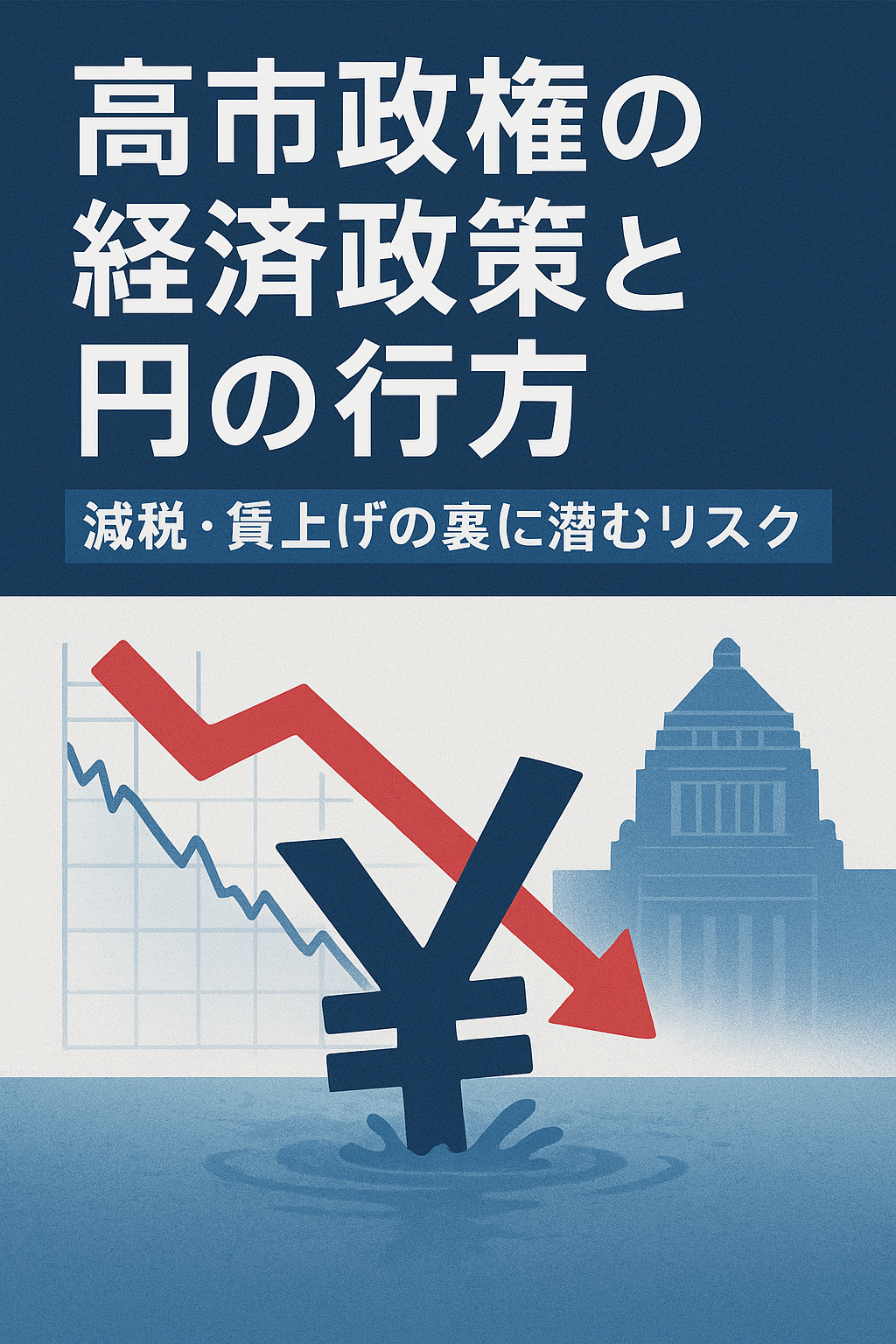高市政権の金融・減税・ベースアップ政策と「円の価値」への懸念
先日、高市 早苗氏率いる政権が発足し、経済政策の方向性が改めて注目を浴びています。今回は、「金融政策」「減税・税制支援」「ベースアップ(賃上げ支援)」という三大テーマにフォーカスしながら、私自身が感じる「これ、円の価値が下がる政策ではないか?」という観点から整理してみます。
1.政策の大枠:成長と手取り増、そして積極財政
まず押さえておきたいのは、高市政権が掲げる経済の大局観です。高市氏は自身の所信表明などで、「責任ある積極財政」を掲げ、「経済安全保障・エネルギー・食料を含む危機管理投資」を強調しています。 また、給付付き税額控除や基礎控除の引き上げなど、働く世代・中間所得層の手取りを増やす方向の政策も打ち出しています。
言い換えれば、「所得を増やし、消費を刺激し、経済を成長させよう」という攻めの姿勢です。一方で、その背景には、財政支出を拡大する、あるいは税支援を行うということで、「支えるための財源・借金・将来負担」という構図も見えてきます。
2.金融政策:日銀・為替・金利の関係
次に金融政策の側面です。政権・党内のスタンスとして、金融政策は基本的に独立機関である 日本銀行(日銀)に任せるという姿勢を示しつつも、「政府と日銀が認識を共有・連携を強める」姿勢が明らかになっています。
しかしながら、市場では「高市氏が選ばれた場合、金融緩和長期化・低金利維持」という見方が出ており、その結果として「円安」が進む可能性が指摘されています。
たとえば、金利が低いままだと海外の通貨に比べて円資産の魅力が落ち、資金が他国通貨に流れやすくなります。これが「円の価値下落(円安)」につながる可能性があります。また、緩和的な金融政策が続けば、国内で物価が上がり、それも円の実質購買力を弱める要因になり得ます。
3.減税・税制支援:手取り増だが財源の課題も
政権が掲げる減税・税制支援には、具体的には以下のようなものが挙げられています:
所得税の基礎控除引き上げや「年収の壁」を和らげる制度設計。 給付付き税額控除の導入検討。 燃料税・ガソリン税などの暫定税率見直しなど、物価高対策としての減税。
これらは、家計の「手取り」を直接増やし、生活を下支えするという意味では歓迎される方向です。特に、中間所得層・働く世代にはわかりやすい恩恵が期待できます。
ただし、問題は「その財源」がどう確保されるかです。減税や税額控除を拡大し、支援を厚くすると、政府の収入が減ったり、支出が増えたりするため、国債発行などによる債務負担増というリスクが出てきます。実際、政策解説では「必要なら赤字国債をも厭わない」という文言も出ています。
この「支援を手厚くする → 財源をどうするか」という構図が、後述する「円の価値下落につながる」という懸念につながります。
4.ベースアップ(賃上げ)支援:賃金を上げて消費を喚起
賃上げ支援、いわゆるベースアップの方向も打ち出されています。政権は企業に対して「賃上げを促す税制優遇」などを検討しており、賃金が上がることによって消費が拡大し、成長を促すという構図です。
賃上げが実現すれば、働く人にとっては直接のプラスで、購買力も上がるため、経済全体には良い影響を与える可能性があります。しかし、ここでも注意点があります。賃上げが一気に進むと企業のコストが上がり、それを転嫁して価格が上がれば「インフレ圧力」になる可能性があります。さらに、賃上げ→消費拡大→需給逼迫という流れになれば、物価が上がり、円の実質価値が下がるリスクもあります。
5.なぜ「円の価値が下がる政策」になると感じるか
ここまで説明してきた政策群を総合すると、私が「円の価値が下がるのではないか」と考える理由は次の通りです。
積極財政+減税+賃上げという“支出拡大型”の政策構図 支出を増やし、減税・支援で手取りを増やし、賃上げで消費を喚起するという政策は、少なくとも短期的には需要を拡大させる方向にあります。政府が「必要なら赤字国債」という選択肢を示していることから、政府の債務残高拡大・財政健全化への懸念も生まえています。通貨の信認・国の信用が揺らぐと、為替では「円を持つ魅力」が低下し、円安に繋がりやすいです。 低金利・金融緩和長期化の可能性 もし日銀が長期間にわたり低金利を維持し、金融緩和的な姿勢を続けるなら、海外のより高金利通貨に資金が流出し、円が売られやすくなります。市場関係者は「緩和継続=円安リスク」という見方をしています。 消費拡大 → 物価上昇インフレ → 実質購買力低下 減税・賃上げで消費が拡大すれば、一定程度物価上昇圧力がかかる可能性があります。特に日本は輸入依存が高く、円安が進むと輸入物価が上がるため、インフレが加速しやすい構造です。このとき、円1枚で買えるモノの量が減る=円の価値が実質的に下がる、という関係があります。報道でも「円安による輸入物価上昇」が物価高の主因といった分析が出ています。 為替・輸入物価の双方向リスク 円安になると、輸入に頼る資源・エネルギー・食料の価格が上がります。すると国内物価が上がり、さらなるインフレ・賃上げ要求・金融対応という悪循環に陥るリスクがあります。つまり、政策が“円安を加速する”方向なら、それが国民生活にとってコスト上昇=円の価値下落というかたちで帰ってくることになります。
6.ただし“即断”はできない:留意すべきポイント
とはいえ、「円の価値が必ず下がる」と断定するのも早計です。ここにはいくつかの留意点があります。
政策の実施規模・時間軸・優先順位がまだ不透明です。少しずつ手を打つという見方も出ています。 為替や金融政策は国内要因だけでなく、海外金利・米ドルの動き・地政学リスクなど多くの外部要因に左右されます。 円安=必ず悪というわけではなく、輸出企業には追い風になる場合もあります。実際、マーケットでは高市政権が株式にはプラスという見方も出ています。 また、「責任ある積極財政」という言葉通り、将来的な財政健全化や供給力強化(成長力の底上げ)という中長期視点が政策には含まれており、これが実現すれば逆に円の信認回復・円高回帰という可能性も否定できません。
7.ブログとして読者に伝えたいこと
もしこのブログを読んだ方に伝えたいメッセージを整理するなら、以下のようになります。
今の高市政権の政策方向は、「手取り増・賃上げ・成長投資」といった、働く人・中間層・経済を活性化させようという流れが明確です。 ただし、同時に「支出拡大・低金利・為替リスク・輸入物価上昇」といったマクロのリスクもはらんでおり、特に“円の価値(為替・実質購買力)”という観点からは警戒すべき構図があります。 資産形成・投資を考えるなら、「円単位で持っておくリスク」「インフレ耐性」「為替変動」なども視野に入れておくと良いでしょう。たとえば外貨資産、海外分散、インフレ連動型資産などが選択肢として出てきます。 政策は動き始めたばかりで「どこまで」「いつまで」「どの規模で」実行されるかが鍵です。時間軸・手法・財源・成長実現度合いをウォッチしていくことが大切です。 最後に、「円の価値が下がる」という可能性を意識しつつも、それが必然ではなく“可能性”として備えるというスタンスが、読者にとって実践的だと思います。
結びに
まとめると、今回の高市政権の政策は、手取り増・賃上げ・成長投資というポジティブな側面がある一方で、円の価値に関しては警戒すべき要素が複数あります。私自身が「円の価値が下がる政策になるのでは」と感じるのは、まさに「積極財政+低金利+消費拡大」という構図が、為替・物価・通貨信認という観点から見たときに“円安・円価値低下”と親和性があるからです。
けせんぬ|30代 資産形成ブロガー & 多資格ホルダー
20代から資産形成を始め、現在は準富裕層に到達。
毎月103万円をインデックス投資に積み立てながら、資格取得と実務スキルで人生の安定と自由を追求中。
保有資格:
消防設備士(甲4・乙3〜6)、危険物取扱者(乙種全類)、第2種電気工事士、
第2種消防設備点検資格者、2級ボイラー技士、FP2級(R5.9合格)、食品衛生責任者