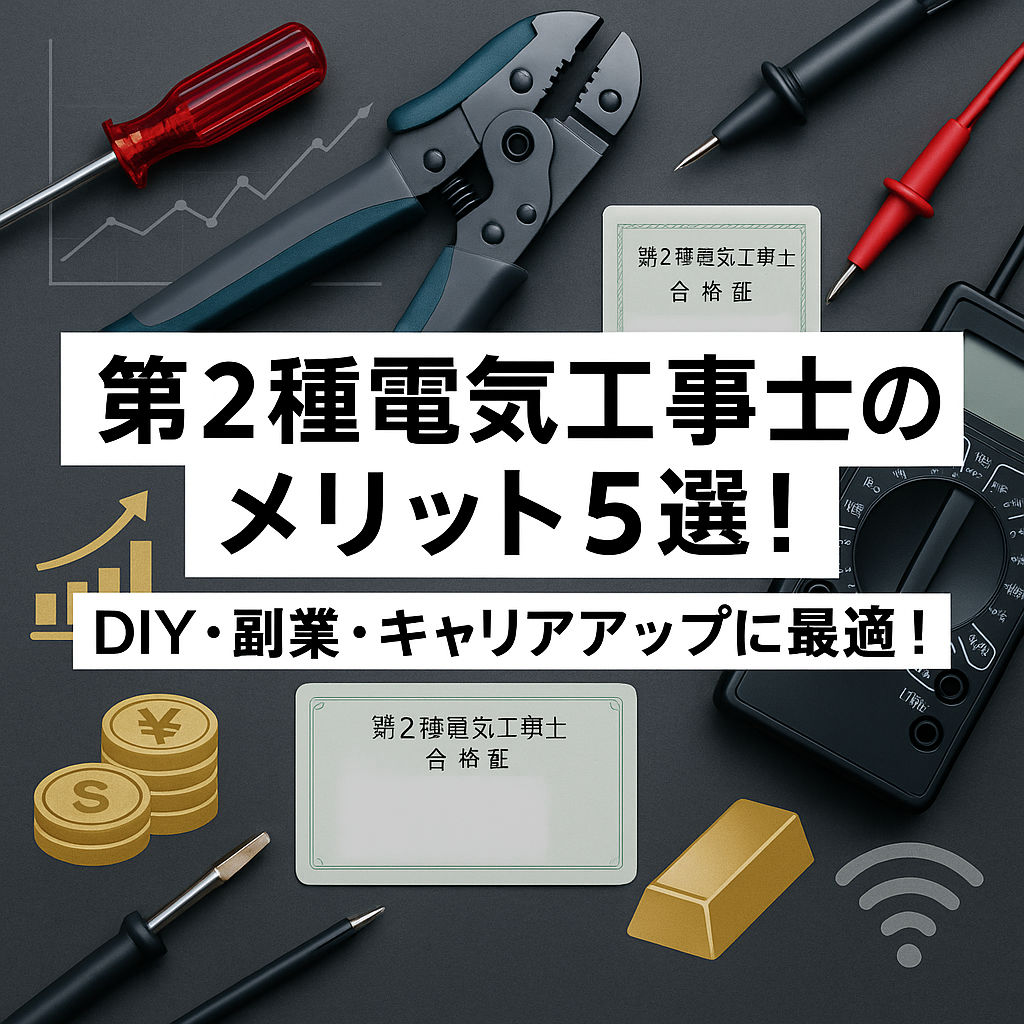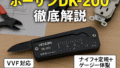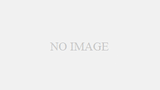こんにちは!
この記事では、第2種電気工事士の技能試験に欠かせない**「複線図の書き方」**について、電気初心者の方にもわかりやすく解説します。
複線図は、単なる作図ではありません。**配線ミスや欠陥を防ぐための「設計図」**です。これを正しく描けるようになることで、技能試験の合格に大きく近づきます!
そもそも複線図とは?
筆記試験で学ぶ「単線図」は、配線の流れをシンプルに示した図で、電源・スイッチ・器具の接続関係を1本の線で表しています。
一方で「複線図」は、実際に配線するケーブル・線の色・本数などを具体的に示した作業用図面です。技能試験ではこの複線図をもとに、正確に電線を切り出し、結線していきます。
【基本】複線図を書く手順
1. 単線図を確認する
まずは問題に記載された単線図を確認しましょう。図には次のような器具が描かれています。
電源(100V・200V) コンセント(接地側、非接地側) スイッチ(片切・3路・4路) ランプ(表示灯・引掛シーリングなど)
2. 器具の配置をそのまま書き写す
白紙のノートや方眼紙に、単線図と同じ配置で器具を並べて描きます。ポイントは**スイッチ・ランプ・コンセントの「向き」と「順番」**を守ること。
※複線図の向きが間違うと、配線もミスしやすくなります。
3. 電源から線を引く(黒・白・緑の基本)
複線図では実際の電線の色を使って描いていきます。
黒線(非接地側):スイッチや負荷につながる主電線 白線(接地側):中性線、主にコンセントやランプの白端子へ 緑線(アース線):金属部分や接地端子へ
4. 器具ごとに接続線を書く
ここが複線図のキモです。以下のポイントを守りましょう。
**スイッチとランプのつながり方(片切・3路・4路)**を正確に描く **ジョイント部分(リングスリーブや差込型コネクタ)**を丸で囲んで記号化 線の重なりや交差を見やすく配置
よくある器具と接続のコツ
● 片切スイッチ+ランプ
黒線をスイッチ→ランプへ接続。白線は電源からランプへ直接。
● 3路スイッチ
スイッチA・スイッチBの間に2本の渡り線、どちらがL・Tかを明示。
● コンセント
接地側(白)・非接地側(黒)の区別をしっかり描く。記号は「|」=接地側。
練習におすすめの方法
● 市販の「複線図練習帳」を使う
ホーザンやツノダなどから、練習ノートやワークブックが販売されています。
● 方眼ノートを使って自分で描く
1マス1cmの方眼ノートが最適。配線の長さ・交点もきれいに描けます。
● 動画やYouTubeで手順を見る
図面だけではイメージが難しい方は、実際の作業動画を参考にするのも◎。
ミスを防ぐためのチェックリスト
□ 白・黒・緑の線が正しいか? □ スイッチの接続先が正確か? □ リングスリーブの接続位置に印をつけたか? □ コンセントや表示灯の向きが正しいか?
けせんぬ|30代 資産形成ブロガー & 多資格ホルダー
20代から資産形成を始め、現在は準富裕層に到達。
毎月103万円をインデックス投資に積み立てながら、資格取得と実務スキルで人生の安定と自由を追求中。
保有資格:
消防設備士(甲4・乙3〜6)、危険物取扱者(乙種全類)、第2種電気工事士、
第2種消防設備点検資格者、2級ボイラー技士、FP2級(R5.9合格)、食品衛生責任者