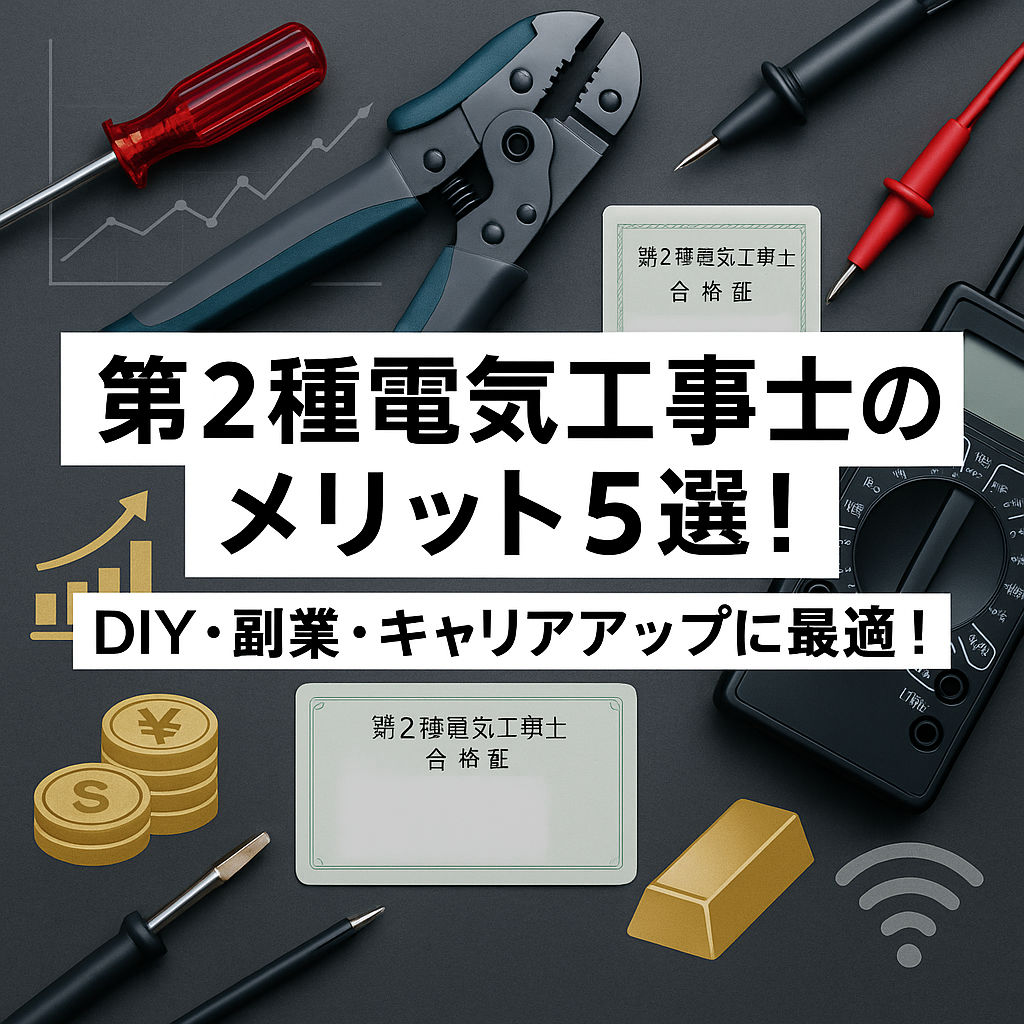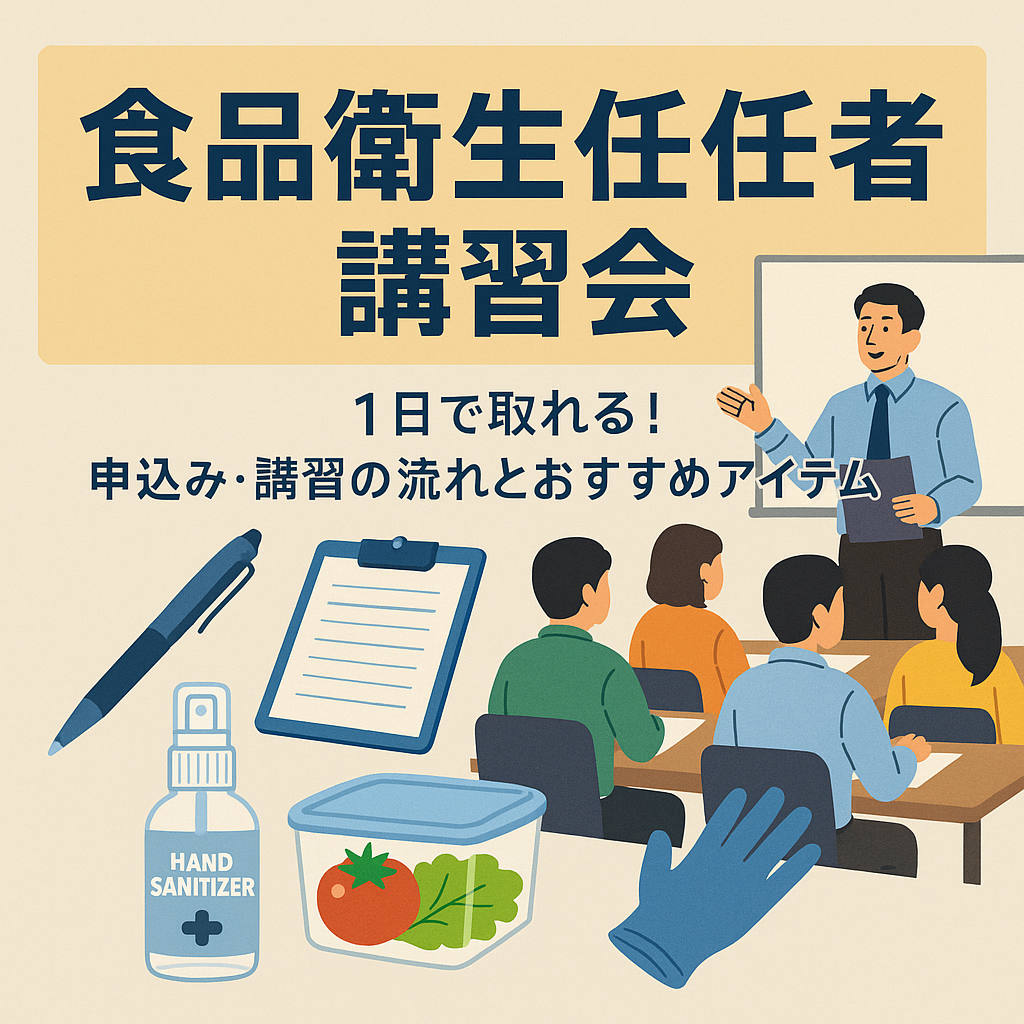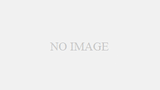こんにちは、けせんぬです。
今日は「第2種電気工事士」の筆記試験本番という方も多いと思います。
これまでしっかり勉強してきた皆さん、本当にお疲れさまでした。あとは落ち着いて試験に臨むだけです。
この記事では、試験当日に気をつけるべきことと、最終確認として目を通しておきたい勉強内容について、直前のタイミングで確認できるようまとめました。試験会場へ向かう途中や、会場での待ち時間などにぜひ読んでみてください。
1. 試験当日に気をつけること
(1) 持ち物の再確認
筆記試験当日は、必要な持ち物を忘れないように注意してください。以下はチェックリストです。
受験票 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど) 鉛筆またはシャープペン(HB以上推奨)、消しゴム 腕時計(会場に時計がない場合があります。スマートウォッチや音が出るものはNG) 必要であればメガネ 上着や羽織れるもの(会場の温度調整が合わないことも)
試験前にコンビニで確認しながら準備するのもアリですが、前日の夜にはすべてカバンに入れておくと安心です。
(2) 試験会場での心構え
余裕を持って出発:事故や電車遅延に備えて、最低でも30分は早めに到着するつもりで出発しましょう。 会場では静かに:会場では緊張している人も多いです。無駄なおしゃべりやスマホ操作は控え、周囲への配慮を忘れずに。 トイレは事前に:試験中にトイレに行くと集中が途切れてしまいます。開始前に済ませておきましょう。 リラックスする:緊張しすぎず、深呼吸して「いつも通り」を心がけてください。今までの努力を信じましょう。
2. 筆記試験直前に確認しておきたいポイント
筆記試験では、過去問と同じような形式の問題が多く出題されます。ここでは「直前に見るべき分野とその理由」を解説します。
(1) 配線図記号とその用途
配線図には電気記号が多く登場します。特にスイッチ、コンセント、表示灯、リレーなどの基本記号は確実に覚えておきたいところです。 問題文に図がある場合は、図から読み取れる情報をもとに素早く判断できるように、パターンを押さえておきましょう。
(2) 単位と計算式の確認
電流(A)、電圧(V)、抵抗(Ω)、電力(W)の基本的な関係式 例) オームの法則:V=IR 電力:P=VI=I²R=V²/R ヒューズ選定や電線の太さの問題でよく使います。数値を暗記するよりも式を理解しておくのがポイントです。
(3) 電線と配線方法
VVF、CVV、EM-EEFなどの電線の種類と用途。 配線方法(隠ぺい、露出、金属管など)や、その施工条件や制限も重要。 よく出るパターン: 壁内に使える電線は? 屋外で使える管は?
この分野は正解が明確なので、覚えておけば確実に得点できます。
(4) 法規(電気設備技術基準、内線規程)
問題文の言い回しがややこしいこともありますが、数字に注目すれば正答できるものもあります。 例: コンセントの設置間隔 アースの接地抵抗値の基準(D種は100Ω以下など)
(5) 過去問で頻出のトピックをざっと確認
過去3年分の問題を見て、「毎年出てるな」と感じるテーマは、出る可能性が高いです。 例えば、「リングスリーブの選定」「端子台の接続方法」「絶縁抵抗測定器の使い方」など。
「問題と解答だけを眺めて、どこがキーワードか」に注目しておくと、短時間で頭が整理できます。
3. 解答のコツと心構え
迷ったら飛ばす:わからない問題で時間を使いすぎないように。後回しにして、まずは確実な問題を取る。 マークミスに注意:特に選択肢のずれは致命的。見直しの時間を5分でもいいので確保しておきましょう。 合格ラインは60点:全50問中30問正解すればOK。満点は必要ありません。6割正解できれば合格です。
おわりに
試験当日は、何より「落ち着いて、これまでの実力を出すこと」が大切です。多少わからない問題があっても、焦らずに1問ずつ丁寧に向き合えば、必ず結果はついてきます。
そして、筆記試験が終われば次は技能試験が待っています。今日の試験が終わったら、1日しっかり休んで、次のステップに備えましょう。
それでは、受験される皆さんの健闘を心より祈っています!
けせんぬ|30代 資産形成ブロガー & 多資格ホルダー
20代から資産形成を始め、現在は準富裕層に到達。
毎月103万円をインデックス投資に積み立てながら、資格取得と実務スキルで人生の安定と自由を追求中。
保有資格:
消防設備士(甲4・乙3〜6)、危険物取扱者(乙種全類)、第2種電気工事士、
第2種消防設備点検資格者、2級ボイラー技士、FP2級(R5.9合格)、食品衛生責任者